「バセドウ病」
そう診断され、処方された薬――“メルカゾール”を飲み続けていてもなお、僕の身体を蝕んでいる症状は続いていた。
「この病気は、本当に治るのだろうか」
そんな考えが頭をよぎるようになり、徐々に“焦り”のような感情が、胸の奥で膨らんでいった。
一方で、職場での僕に対する周囲の視線は、温かいものに変わっていた。
「バセドウ病」という病名が明らかになったことや、僕自身が以前とは比べものにならないほど痩せ細っていたこともあり、同僚や親方は、心配の声をかけてくれることが多くなっていた。
実際、僕の仕事ぶりの凋落は凄まじかった。
朝礼が終わり、作業に取りかかってすぐに、まるで“マラソンを走り切った後”のような状態になり――
“少し作業をしては休む”ということを、繰り返すことしかできなかった。
「動きたくても動かない」
それが、僕の身体を表すのにぴったりの言葉だった。
同じ現場で働いている父は、そんな僕を見て気を遣ってくれているのか、
「辛くなったら、いつでも休んでいい」
そう、不器用だけれど優しい言葉をかけてくれていた。
申し訳ない気持ちで、胸がいっぱいになった。
それまで常に一緒の現場で作業しながら、僕に技術の継承をしてくれていた父――
その“想い”や“期待”に、応えられないかもしれない。
鉛のように重い身体を抱えながら、そんな考えが浮かんでは、それを打ち消すように必死に身体を動かしていた。
そんな日々が続く中、メルカゾールのおかげか、ようやく体重減少や筋肉分解は落ち着き始めた。
だが、それでも疲労感や感情の起伏の激しさは、いっこうに治まる気配がなかった。
「この症状は、一体いつまで続くのか」
その時の僕の中には、明確なかたちを持った“不安”や“焦り”が、はっきりと影を落としていた。
けれども現場にいる時は、なんとか以前と同じペースで作業ができるように、必死に喰らい付いていた。
それでも――
自身の限界を、感じつつあった。
道具を取るために屈むだけでも、“身体の奥から熱を帯びていくような感覚”
脚立に乗るだけでも、“長い坂道を登った後のような疲労感”
「先が、まったく見えない」
それが、この時の僕の状態だった。
だが僕は、自身の限界を感じながらも――
“その不安を抱えたまま”、日々、現場に立ち続けることしかできなかった。
次回予告
――暗闇の中に、差し込む一筋の光。
それは、誰かの言葉――それとも、想い。
崩れかけた心に触れた、小さな温もり。
逃げ出したくなる日々の中で、唯一、立ち止まらせてくれた存在。
次回―第4章『彼女の存在』
――生きる理由が、そっと、傍にあった。


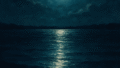

コメント