〜憧れと始まり〜

この歩みの記録を開いていただいてありがとうございます。
ここでは僕の今までの歩みを小説風にして書いていこうと思います。
できるだけ当時の出来事や人物、僕自身の心情などを思い出して書いていきますが、人物名などは架空の名前で書いていきます。
僕の名前は”リック”で進めていこうと思いますのでよろしくお願いします。
春、桜がひらひらと舞い散る季節。
僕は真新しい制服に身を包みながら、緊張と希望が入り交じった気持ちを胸に、校長先生の挨拶を聞いていた。
今日は高校の入学式だった。
僕は体育館でパイプ椅子に座りながら、ちらりと目立たないように周りを見渡してみた。
両隣には制服を着崩し、髪を染めてワックスで固め、おまけにピアスまで着けて気怠そうにしている、見るからに”やんちゃそうな”2人組が座っていた。
“これからはこういう人達とも普通に喋れるようにしよう”
僕は心の中で密かにそう決心していた。
中学生の時までの僕は、クラスメイトと普通に話すことすら満足にできなかった。
人と話そうとすると頭が真っ白になり、鼓動が早くなって言葉が出なくなる。
そんな自分が恥ずかしくて、人の前に立っていることすら辛くなるのだ。
けれども、高校への入学を機にそんな自分を変えようというわけだ。
入学式を終えると、先程の2人組が話しかけてきた。
「入学式ダルかったな。お前も同じクラスだろ。」
2人のうちの1人がそう話しかけてきた。
心臓がどくりと跳ねる。
「そ、そうみたいだね。よ、よろしく。」
なんとか笑顔を作り、言葉を返す。
だがやはり、それまで人と話すことをしなかった脳は言葉を滑らかに出してはくれなかった。
2人は怪訝そうに顔を見合わせ、少し笑っていた。
──やってしまった
やはり、そう簡単には変わることはできないのか。
僕の心に暗い気持ちが押し寄せてくる。
僕は一度落ち込んでしまったら、しばらくは立ち直れない。
ずっと頭の中でぐるぐると失敗を引きずってしまうのだ。
とりあえず、割り当てられた教室に行こう。
僕は肩を落としながらも同じクラスの生徒達の集団について行った。
しばらく歩いていると、これから僕が学校生活を送るであろう教室に着いた。
私立にもかかわらず、教室はどこか古く小汚い印象だった。
少し薄暗い電球に、古い木材を使っているであろう床は歩く度にミシミシと音を立てていた。
そして見渡す限り、男子生徒しかいなかった。
どうやら僕のクラスは男子しかいないクラスらしい。
他のクラスメイトは不満だったようだが、僕は有り難かった。
女子よりも男子の方がまだ緊張しなくて済むからだ。
「俺が今日から3年間お前らの担任になる小見山だ。」
教壇には、これから3年間担任になる小見山先生が立っていて、自己紹介を始めていた。
僕の通うことになるこの学校は私立の高校だ。
学科は普通科、体育科、工業科、特進科の4つがある。その中で僕は普通科で入学した。
どうやらこの学校は3年間同じクラスらしい。
そしてこの学校の大きな特徴は、運動部が強いことだった。
特に体操部と水泳部はオリンピック選手も輩出しているほど、力を入れているらしい。
と、小見山先生の話が終わったらしく、今日はこれまでと先生は締め括った。
最後に思い出したように――
「ああそうそう、部活に入りたい奴は入部届けを提出するように。」
部活――
僕がこの高校に入った1番の理由だ。
“剣道部に入る”
僕は中学3年生の頃から、そう心に決めていた。
きっかけは、あるノベルゲームだった。
ノベルゲームとは、小説のように物語を読んでいくゲームだ。
そのノベルゲームの中でも、僕は”fate”という作品にとても心動かされた。
特にその作品の主人公に憧れていた。
彼は作中でも決して強い方ではなく、才能も特別あるわけではなかった。
けれども彼は――”心が強かった”
――何度倒れても
――何度傷つけられても
彼は立ち上がり、自らの限界に挑み続けた。
僕はその姿に、人生で初めて”心が震える”体験をしたのだ。
――彼のような心の強い人間になりたい
僕は心の底からそう思った。
そのために、厳しいことで有名なこの学校の剣道部に入部して、自分を強くしたかった。
あの主人公も物語の途中から剣を習っていた。
決して才能があるわけではなかったが、努力を続け、最終的には才能あふれる傑物達にも引けを取らない実力を身に付けていた。
僕も厳しい環境で剣道の鍛錬を続けていけば、彼と同じようになれると信じていたのだ。
「リック、もう学校は終わった?」
入学式に一緒に来てくれていた母が、学校のエントランスで待ってくれていた。
「終わったよ、めっちゃ疲れたから早く帰りたい」
母に会うと、緊張の糸が緩んだのか入学式の疲れがどっと押し寄せてきた。
母はにっこりと笑って、
「じゃあ帰ろうか。帰りに美味しいお菓子でも買って帰ろうね」
母は、僕が甘いものが好きなのを知っているので、よくこうしてお菓子を買ってくれるのだ。
エントランスから校門を出て、僕と母は駅に向かう。
僕の家から学校までは、電車で約30分のところにあった。
今まであまり電車に乗る機会がなかったので、電車通学というのは密かに憧れていた。
「良さそうな学校でよかったね。
クラスはどう?うまくやれそう?」
電車に揺られながら、母が少し心配そうに僕に尋ねてくる。
「まだ分からないけど、これから頑張っていくよ」
僕は当たり障りのない返事をしながら、窓の外に目を向ける。
次々と流れゆく景色を眺めながら、僕は密かに決意をする。
“明日、剣道部に行って入部の意志を伝えよう”
緊張で早鐘を打っている鼓動を感じながら、僕は明日へ想いを馳せていた。

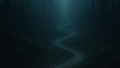
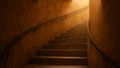
コメント