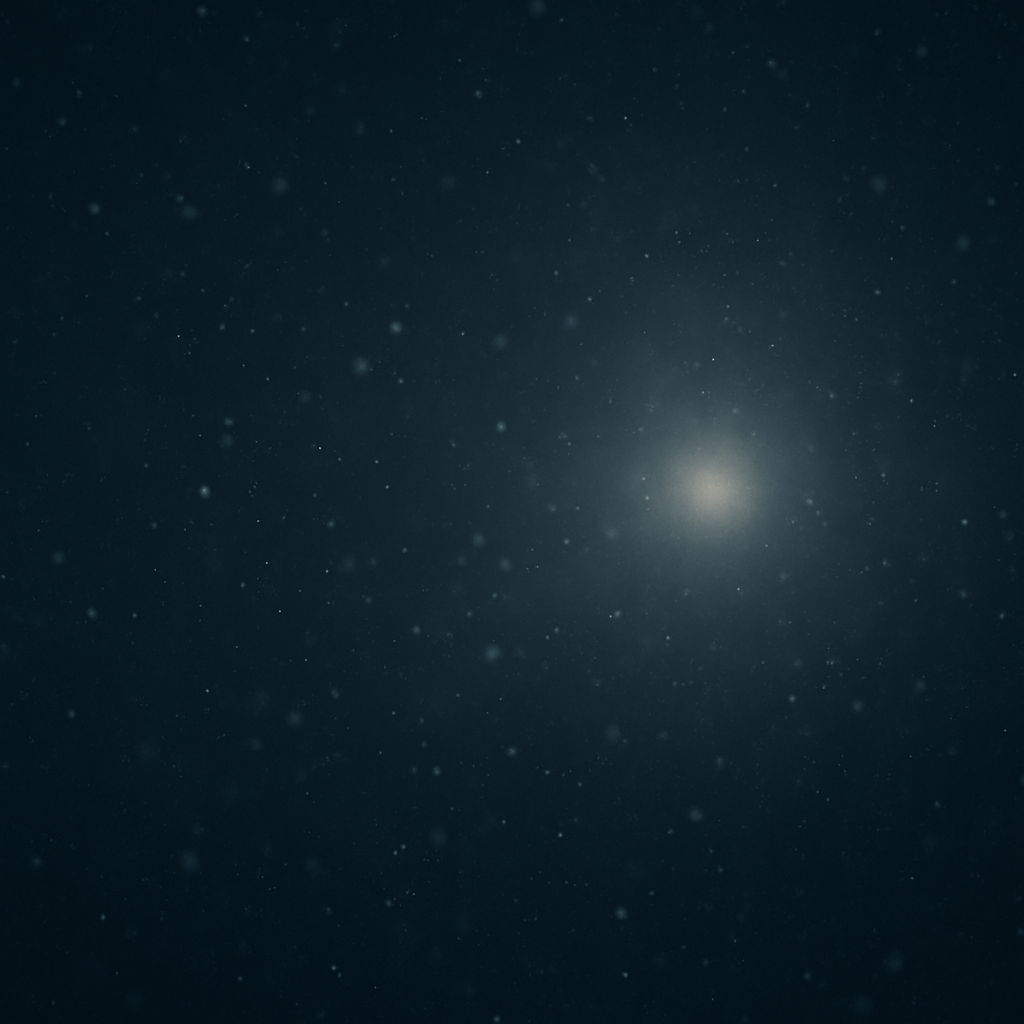
僕は自分のことを”冷たい”と思っている。
分かち合えない、優しくない、他人に寄り添えない──
特に何かをしたわけでもない。ただ、人のことで感情が揺れない。故に、”冷たい”という評価を自分に下していたのだ。
たとえば、妻が飼っていた猫が亡くなったとき。
60万円の治療費を払えば助かる可能性があった。
でも、僕はそれを選ばなかった。
今の経済状況、自分たちの生活、将来への不安──
それらを冷静に考えた末に、「お金は払えない」と判断した。
情ではなく、現実と向き合った末の決断だった。
彼女が泣き崩れていたそばで、僕はただ黙っていた。
その姿を見て「かわいそうだ」と思っても、“悲しさ”そのものが、自分の中に湧いてこなかった。
どこか、自分の内側に、透明な膜のようなものが張られていて──
それが、感情の波をせき止めていた。
そのとき僕は、彼女を慰めようとするよりも、心の奥でこんなことを考えていた。
「命はいつか尽きるものだから、これが寿命だったのだろう。仕方のないことだ。」と──
その冷静さが、自分でも怖かった。
でも、冷静だったからといって、心が冷えていたわけではない。
ただ、自分でも、どう向き合えばいいのか分からなかっただけだった。
彼女は当時の僕と違い、感情を大切にする人だ。
嬉しいときは笑い、悲しいときは涙を流し、時には怒りをあらわにする。
そしてそのすべてを、「一緒に感じてほしい」と願っている。
だが僕は、彼女が涙を流すとき、いつも戸惑ってしまう。
何を言えばいいのか、何をすればいいのか分からないのだ。
一緒に悲しむ“ふり”をするのも、うまくできない。
だから、沈黙することが多くなる。
結果的に、「寄り添ってくれない」「自分のことしか考えていない」と言われてしまう。
──図星だった。
「彼女の友達のほうが、自分の欲しかった言葉をくれた」
そう言われたとき、僕はひどく傷ついた。
けれど同時に、“やっぱり自分は、そっち側の人間にはなれない”という諦めが心に広がった。
この”諦め”は、今までに何度も感じてきた感情だった。
たとえば学生時代──
クラスメイトが皆で喜びや悲しみを分かち合っていたときも、僕はいつも疎外感を感じていた。
なぜなら、他のみんなが思うようには思えなかったからだ。
「自分は、ほかの人たちと違う」
「冷たいから、感情が薄いから」
そうやって自分に言い聞かせて、ずっと諦めてきた。
けれど──
それでも、「彼女の隣にいたい」という思いだけは、諦めきれなかったのだ。

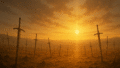
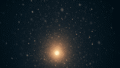
コメント